上流工程に携わりたいが、まだIT業界未経験であったり経験が浅くて自分には早い…
そう思ってしまっている人は多いのではないでしょうか?
この記事では、新人でも上流工程に携われるチャンスやそのメリット・デメリットなどについて解説します。
筆者が新卒で上流工程を担当した経験談も含めて解説するよ!
一般的な上流工程に携わるまでのステップと期間
一般的には上流工程を担当する前に、1〜3年ほど開発業務を経験した後、設計やドキュメント作成、顧客対応を任される流れが多いと言われています。
下流工程で基礎を固めつつ、設計レビューや顧客会議に同席することで、上流スキルを徐々に身につけるパターンが王道とされています。
新人でも上流工程に関われるのか?
では一方で、IT業界未経験者の新人は上流工程を担当することはできるのでしょうか?
結論、
「一次受け案件比率が高い企業、またはコンサル企業であれば十分に可能」
だと思います。
筆者は一次受け案件比率が9割以上のSIer勤務ですが、新卒1年目から上流工程を担当することができました。
一方で、受注案件の大半が下流工程の業務である企業だと、10年以上勤務しなければ上流工程に携われないことも多々あるようです。
新人から上流工程を担当したいなら、一次受け案件比率が高い会社またはコンサル企業に就職すべし!
プログラミングができなくても上流工程は可能?
結論、プログラミングが得意でなくても上流工程を担うことは可能です。
特にITコンサルやPM職では、プログラミング知識よりも調整力や課題解決力が重視されます。
ただし、技術知識がゼロでは現場との意思疎通が難しいため、基本用語や開発フローの理解は必要です。
新人でIT経験が浅いうちは知識をインプットしつつ調整業務を行う必要があり、
僕はこの両立が少し大変でした…
新卒で上流工程を担当して感じたメリット・デメリット
筆者が実際に新卒で上流工程を担当して感じたメリット・デメリットを紹介します。
メリット
以下は事例を交えて詳しく紹介します。
若手から上流工程を経験するメリット
・プロジェクト全体を俯瞰する視点が持てる!
・早期にビジネススキルが身につく!
・キャリアの選択肢が広がる!
プロジェクト全体を俯瞰する視点が持てる
新卒1年目で要件定義会議に参加し、システムの全体像を理解できたことで、その後の業務のイメージがつかみやすくなりました。
システムの規模にもよりますが、新人で下流のテスト工程から担当する場合、担当しているシステムの一部は学ぶことができるが、システム全体の概要を理解するのは難しいことも多いようです。
その点、要件定義から参加できていれば、業務を通じてシステムの概要から学ぶことができます。
早期にビジネススキルが身につく
顧客との打ち合わせで議事録作成や課題整理を行い、ビジネスマナーや提案力が自然と鍛えられました。
キャリアの選択肢が広がる
上流工程を経験したことでPMやITコンサルへのキャリアパスを意識できるようになりました。
デメリット
一方、デメリットと感じることもあったのでご紹介します。
技術力を深める時間が少ない
会議や調整業務に時間を割かれ、業務内でプログラミングや設計をじっくり学ぶ機会が少なかったです。
下流工程から始めた同期と技術力に差が生じていることに焦りは感じました。
勤務時間外に自己研鑽として学ぶことになりますが、業務を通して学んだ方が実践的な知識が身に付くためできれば実務で手を動かしながら学びたいという思いはありました
まとめ
新人だからといって上流工程を諦める必要はありません。
また、若手のうちに上流工程を経験することはキャリアや市場価値を高める上でもメリットは多いと思います。
しかし、上流工程を経験できる企業に入ることが絶対条件となるので、企業選びは慎重に行いましょう!
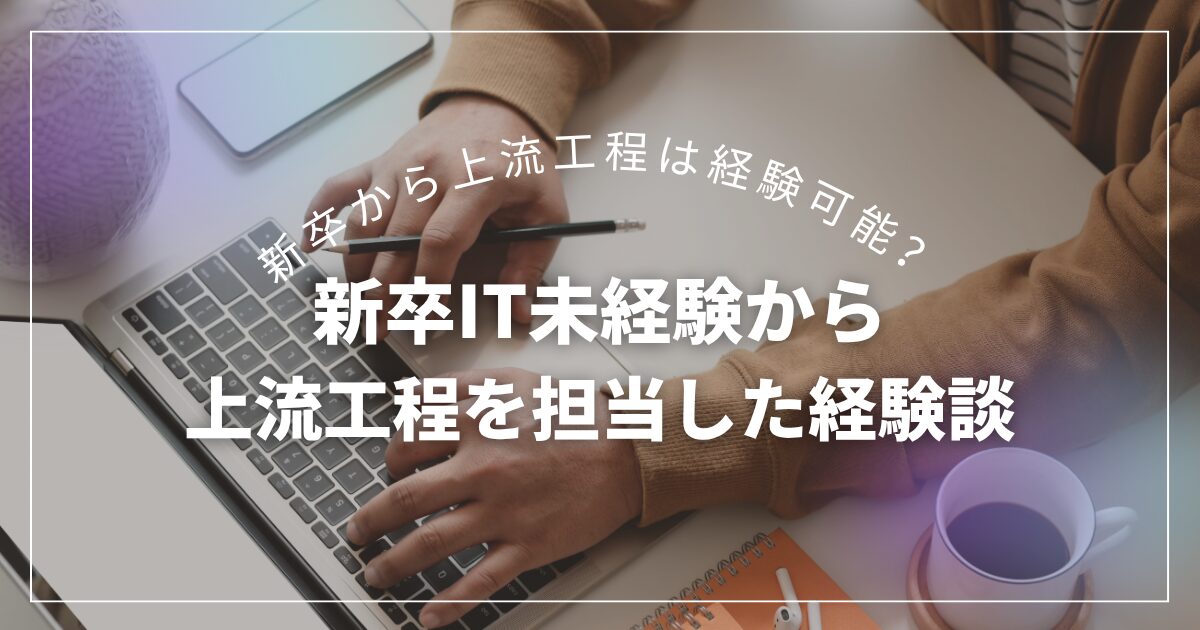
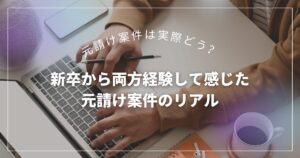
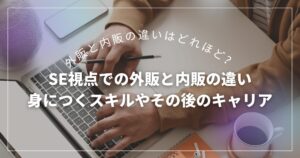
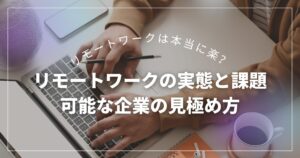
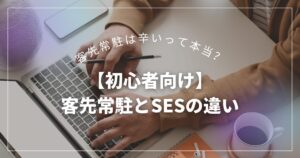

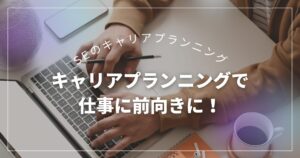


コメント